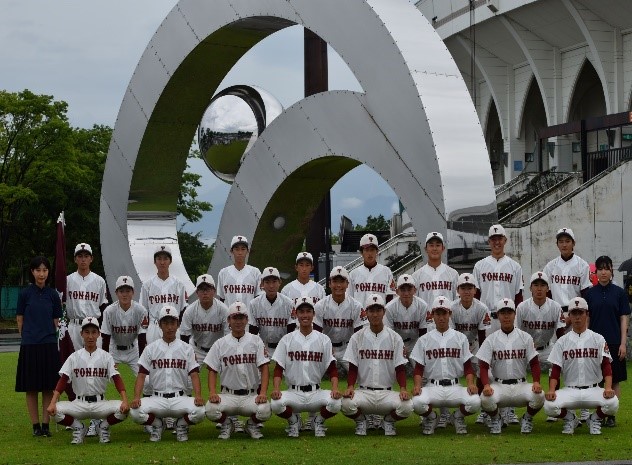卒業式、終業式も終わり、光に満ちた季節がやって来ましたね。3年生は新しい生活に向けて、1年生と2年生は新しい学年に向けて準備を始めていることでしょう。令和6年度も砺波高校の生徒達は様々な所で活躍してくれました。地域のたくさんの人から感謝の声が寄せられています。皆さんは将来社会のリーダーとなり、多くの人に頼られる存在になることでしょう。だから最後に、これからの時代に求められるリーダーについて私の考えを話しておきたいと思います。
リーダーには組織をマネジメントする責任があります。業務マネジメント、財務マネジメント、タイムマネジメント、リスクマネジメント、コミュニティマネジメント等々。私はこれまで、様々なマネジメントの中で「スタッフマネジメント」というものを最も大切にしてきました。何故ならば、このマネジメントは、技術よりも心が優先するからです。
相手の話を聞く→相手の心を確認する→相手の存在を認める→相手に自分の考えを伝える→相手と共有する・・・スタッフマネジメントの一般的なプロセスです。この中で最も重要なのは、相手の存在を認める事です。相手に「貴方は無くてはならない存在だ」と伝えてあげる事です。そして、相手のおかげで自分も変われると感じる事です。
したがって、私が思う真のリーダーとは「周りの人々に最大の敬意(リスペクト)を払い、自分を正しい方向に変える事ができる人」なのです。大国の指導者達に大きな疑問を感じる昨今、マハトマ・ガンジーの言った教訓が胸に染みます。 「世界を変えたければ、あなた自身、世界が望むような『変化』とならなければならない」
Change oneself and change others.(自分が変われば人も変わる) 君達が将来リーダーとなり、多くの人の為に活躍することを楽しみにしています。
学校長 中村謙作